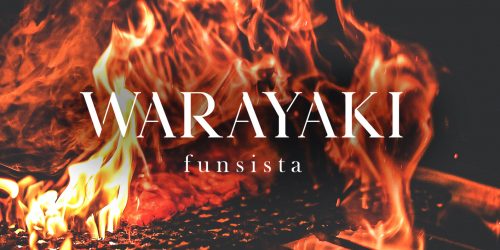年越しの準備はなにをすればいいの?大掃除や年賀状などの意味も紹介

12月になると、「今年も終わりだ」といった気分になります。今年一年を振り返り、思い出にふけることもあるでしょう。
ですが、今年はまだ残っており、来年の準備をしなくてはなりません。準備を忘れてしまうと、慌ただしい年の始まりとなってしまいます。新年を気持ちよく始めるためにも、年越しに向けた準備が必要です。
年越しにはどんな準備をすればいいのか。主に行われている内容を紹介します。
大掃除の準備
年末といえば、大掃除の季節です。新年を気持ちよく迎えるため、隅々まで掃除をして家じゅうを綺麗にします。
大掃除の由来
大掃除の由来は、平安時代まで遡ります。お正月には「年神様」と呼ばれる神様が訪れるとされており、お迎えに失礼がないよう、宮中を綺麗にしていました。
大掃除のタイミングも、今とは異なり12月13日に行われています。これは、旧暦12月13日が万事の大事とされる「鬼宿日」だからです。神様を迎えるための掃除は、神聖な行事と考えられていたため、縁起の良い日が選ばれています。
また、昔は大掃除ではなく、煤払いと呼ばれていました。昔の灯りは油を使用しており、燃やすことで煤が天井などにこびり付き、それを落とすことから煤払いと呼ばれていたのです。
近年でも、煤払いの神事は残っており、神社などでは12月13日に煤払い(大掃除)が行われています。
大掃除を始めるタイミング
大掃除といえば、29日~31日にかけて行うのが一般的です。多くの社会人は28日まで仕事をしており、年末休みとなる29日から掃除を始める人が多いといえます。
昔とは違い、今の人は神様をあまり意識していません。そのため、都合の良い日に大掃除を始めています。
ですが、年末にバタバタ準備するのは、新年を迎えるうえであまり良くありません。年末が忙しいと、来年も忙しい年になってしまいます。
来年が落ち着いた年になるよう、12月に入ったら少しずつ始め、年末休みとなる29日までには、終わらせておくようにしましょう。
大掃除がダメな日もある?
大掃除は、元々神事として行われてきました。そのため、仏滅などの縁起の悪い日は、大掃除を避けるべきといった考えもあります。
ほかにも、4が付く日は「死」を連想し、9が付く日は「苦」を連想することから、同様に避けた方がいいともいわれています。
もちろん、近年の大掃除は神事として行われていませんので、気にする必要はないかもしれません。あくまでも、「そのような考えがある」程度に思ってください。
年賀状の準備
年越しの準備といえば、年賀状の準備も忘れてはいけません。SNSが流通した近年においては出さない人も多いですが、正月の代表的な季節行事として知られています。
年賀状の目的
年賀状の目的は、主に遠方へ住む人への挨拶回りの代わりです。遠方に住むことから気軽には会いに行けないことから、代わりに年賀状で新年の挨拶を送っていました。
たとえ年に一度のやりとりとはいえ、連絡を取ることは関係を保つことにつながります。関係を途切れさせないためにも、年賀状は送られてきたのです。
また、近年では生存確認の代わりといった見方もされています。普段会わないことから相手の状態が分からず、それを確認するため、年賀状を出すといった人も少なくありません。
とはいえ、近年は電話やSNSで簡単に連絡がとれるため、年賀状の意味がなくなってきています。
目上の人に礼儀を尽くすために出す場合がほとんどであり、年々年賀状が出される件数は減りつつあります。
年賀状を出すタイミング
年賀状を出す際は、12月25日までに出すようにしてください。12月25日までに出せれば、元旦に年賀状が届きます。
12月25日を過ぎても年賀状は届きますが、1月7日以降だと寒中見舞いになってしまいます。12月25日に間に合わない場合でも、せめて三が日までには、届くよう準備をしてください。
年賀状は手書きの方が良い?
結論から言えば、どちらでも構いません。あくまでも挨拶周りの手紙ですので、どちらであっても気にしない人の方が多いといえます。
ただ、手書きの方が感情がこもっており、温かみがあります。オリジナリティもあるため、貰った方としては嬉しく思うでしょう。
とはいえ、関係が広いと年賀状の枚数も多くなり、手書きで出すのは一苦労です。仕事や家事、ほかの年末準備が忙しく、年賀状だけに時間を割くわけにはいきません。
そのため、基本的には印刷で準備をし、特別な相手に対してだけ、手書きで準備をすると良いでしょう。
年越しそばの準備
年末の食事といえば、年越しそばが定番です。毎年多くの人が、年末にそばを茹でて年末を過ごしています。
年越しそばの意味
年越しそばを食べる意味は、「そばのように細く長く生きられるように」といった願いをこめるためです。来年以降も良い年となるよう、年越しそばで願掛けをします。
ほかにも「そばのように家族の縁も細く長く続くように」といった願いや、「そばのように厄や苦労が簡単に断ち切れますように」といった願いもあり、さまざまな願いを込めていただいています。
年越しうどんでも大丈夫?
地方によっては、そばの代わりに年越しうどんを食べるそうです。うどんには「運を呼ぶ」といった語呂合わせや、形状から「太く長い人生になるように」といった見方もされ、そばとは違った願いが込められています。
あくまでも縁起を担ぐためのものであり、重要な意味があるわけではありません。好きなように願いを込めて、好きなものをいただいてください。
年越しそばを食べるタイミング
年越しそばは、12月の31日にいただきます。食べるタイミングも特に指定されていませんので、好きなタイミングでいただくといいです。
ただ、注意点として、年を越す前に食べきってください。年越しそばはあくまでも「今年の厄を切り、来年の長寿を願う」ものであり、来年に持ち越しては意味がありません。
除夜の鐘を聞きながら食べようと考えている人は、残りの時間に注意しましょう。
お正月の準備
年が明けたらすぐにお正月です。年末の準備とともに、年明けの準備も必要になるでしょう。
おせちの準備
おせちは、漢字で「御節」と書き、季節の節目を指す言葉です。正月を含む特別な節目の時期に、特別な振る舞いとしておせちが提供されてきました。
元々は、神様への奉納も目的とした料理でしたが、江戸時代になると幕府が季節の節目を公式な祝日(節句)と定め、それに伴い庶民の間でも食べられるようになります。
現在では、そのような経緯を気にせず、最も大きな節目であるお正月のみでおせちが食べられているわけです。
また、お正月に食べられている理由には、お正月はほとんどの商店が休みなのも挙げられます。どの店も正月休みとなり食材が購入できません。そのため、保存性の良い食材をおせちに詰め、三が日を過ごしていたのです。
おせちには、卵が多いことから子孫繁栄が願われる「かずのこ」や、マメに働く(勤勉である)ことを意味する「黒豆」などが入れられ、今年一年の幸運や抱負を願掛けしています。
近年はおせちを食べない家庭も増えてきていますが、今年一年を良い年にするためにも、ぜひおせちをいただいてください。
門松の準備
近年はあまり見かけなくなってきていますが、門松もお正月に用意しておきたいものです。
門松を飾る意味は、年神様が訪問する目印とするためです。門松を飾ることで我が家の場所を年神様に知らせ、訪れてもらうことで幸運を授かります。
そのため、門松がないと年神様は訪れてくれません。運気を授かることができず、運が悪い年になってしまうでしょう。
また、鏡餅を用意する意味も同じです。鏡餅が年神様の依り代となるため、鏡餅がないと居ついてくれません。
今年を良い年にするには、門松や鏡餅を用意することが大切です。
ちなみに、飾るスペースがない場合は壁掛けの小さいサイズでも大丈夫です。松を始めとした常緑樹や竹をベースにしてあれば、形も問いません(年神は年を取らないため、常に緑あふれる松などがふさわしい)。
しめ縄飾りなどといっしょに、門松も揃えておきましょう。
まとめ

12月は、年末や正月に向けて、色々な準備があります。「今年もまだある」と考えていると、すぐに準備する時間がなくなってしまうでしょう。慌ただしい年末にしないためにも、コツコツと準備を進めるようにしてください。
紹介した内容以外にも、家庭によっては「新品の物に交換する」「お年玉の準備をする」「初詣や初日の出の準備をする」などもあります。何をするのかをリスト化し、抜けがないよう準備しましょう。
『驚くほど当たる』と話題の奇跡のスピリチュアル診断が今なら初回無料!
恋愛における片思いの相手の気持ちや相性、転職・仕事の運勢、結婚や復縁の相談など、不安なことにメール占いで答えます。
『今後の運勢』知りたい方!今だけ≪無料鑑定≫を体験下さい!
電話占いならこちら↓
口コミで評判の占い師多数在籍!大人気の電話占いが初回全員3000円無料
誰にも言えない大人の悩みや、家庭の悩みなど普段から抱えている不安を鑑定師がズバリと的確に診断いたします。
親身なアドバイスで悩みを解決!あなたのお悩みをご相談下さい!